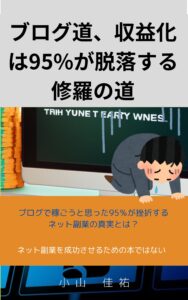日本刀は日本が誇る伝統的な工芸品ですが
一部、再現できない刀があります。
現在の刀工が作る日本刀は江戸時代に確立された新刀と呼ばれる区分の刀になります。
日本刀でも時代によって作り方が変わっており平安時代から安土桃山時代、つまり戦国時代の刀と江戸時代の刀は別物になっている。
古刀について
古刀とは、昔の日本で作られた刀のことを指します。古刀は、日本の歴史や文化、美意識を象徴する重要な文化遺産であり、その切れ味や美しい刀身の彫刻、鍛錬技術などが高く評価されています。
古刀は、主に平安時代から戦国時代にかけての時期に作られたものが多く、その多くが重要文化財や国宝に指定されています。
古刀には、大刀、太刀、短刀などの種類があり、それぞれに独特の形状や特徴があります。
古刀の鍛造技術は、日本独自のものであり、鍛造の過程での火の扱いや鍛錬技術、刃文や模様の作り方など、高度な技術が必要とされます。
また、刀身には刀匠の銘が刻まれることが多く、その銘は刀の評価にも大きく関わっています。
古刀は時代によって上古刀から末古刀までがあります。
日本刀の時代区分は?
- 上古刀・・・・上古時代の刀という意味で古墳時代から平安時代までに作られた刀剣(一般的には日本刀ではない)
- 古刀・・・・・日本刀が生まれた時代の刀、平安時代中期から室町時代後期まで作られた刀
- 末古刀・・・・室町時代後期から安土桃山時代後期で名刀も多いが数打ち(量産品)も多く作られた
- 新刀・・・・・安土桃山時代後期から江戸時代中期に作られた刀
- 新々刀・・・・江戸後期に古刀を再現しようとした時代
- 現代刀・・・・明治9年の廃刀令以降に作られた刀の事
末古刀の時代に古刀の技術が失伝してしまった可能性はかなり高い
名刀を生み出すような刀鍛冶はお抱えになる事も多い
戦の多い時代であればあるほど、刀鍛冶の秘伝は口伝だから伝えられていない可能性があり、弟子に全てを伝えられていない
だから、古刀の技術が失伝している。
古刀は再現できない?ロストテクノロジー
現代刀はたたら製鉄で作られた玉鋼を折り返し鍛錬で不純物を叩き出して作った鋼と鉄を組み合わせて日本刀の形にしています。
古刀に使われた鉄はたたら製鉄で作られたのか?折り返し鍛錬をどうしていたのか?
そういった知識が全く伝わっていない
古刀は一子相伝の口伝だったため記録がなくどんな鉄を使用していたのか分からないと言われています。
日本刀の産地は五箇伝と言われ
- 「大和伝」(奈良県)
- 「山城伝」(京都府)
- 「備前伝」(岡山県)
- 「相州伝」(神奈川県)
- 「美濃伝」(岐阜県)
良質な砂鉄が採れて、良質な水があり、流通に滞りがない場所であったため
刀工が集まり技を競ったわけです。
古刀は地域の特色が地鉄(じがね)に出ていた。
地肌に地方色があるなど特徴的だった。
外国から輸入した鉄なども使われていた
豊臣秀吉が天下統一した後は都市が発展していき城下町でも刀が作られるようになった。
たたら製鉄なども行われるようになっていったが小規模な製鉄所は潰れてしまった。
つまり、古刀はたたら製鉄の技法で作られたのか分からないという事です。
更に江戸時代だと鎖国が始まり輸入した鉄が使えなくなった。
そのため古刀に使われる鉄や混合比率、焼入れ温度などの技法が途絶えてしまった。
たたら製鉄で作られた鉄は不純物が少なく硬い、そのため刀としてはもろくなりがち
そのため新刀では柔らかい芯金に硬い皮鉄で包む構造にしている。
古刀は硬い鋼と柔らかい芯金を練り込んで作られていたりするため
断面図が古刀の方が不均一になっていたりする。
新刀は均一になっている。
古刀の方がよく切れる
古刀の方が新刀よりもよく切れるという現象が起きている。
作刀技術が上がったはずなのに古刀の方がよく切れて粘りもあり
刃こぼれもしにくいという現象が起きている。
江戸期の大業物も古刀から選ばれている。
新刀に使われるのは玉鋼と言われる。
たたら製鉄では鋼を主として含む鉧(けら)塊をつくる鉧押し法(三日押し法)と銑(ずく:銑鉄)をつくることを目的とする銑押し法(四日押し法)の2通りがあります。
玉鋼はたたら製鉄の鉧押し法で作られた鉧から取り出される。
玉鋼という名称が定着したのは明治時代中頃
1532~1554年の頃は白鋼(しらはがね)という玉鋼に相当する上質な鋼が存在した。
古刀に使われる鉄は玉鋼とくらべて不純物が多かったのではないかという説がある。
折り返し鍛錬とは鋼を叩いて伸ばして折り曲げて叩いてくっつけて伸ばして刀身を作る
古刀は折り返し鍛錬で刀身を作っていたのではないか?という説があります。
折り返し鍛錬の際に発生する過飽和酸素鋼(黒錆)が重要なのではないかという話です。
水に濡らしたりしてできる錆は赤錆と言います。
赤錆が侵食すると鉄はもろくなったりします。
折り返し鍛錬で作られたと思われる鎌倉時代くらいの鉄釘は千年持つという事で古寺修復に再利用されたりします。
江戸時代の釘になると100~500年くらいしか持たない
現代、ホームセンターなどで販売されている西洋釘は50年くらいしかもたない
新刀の場合は折り返し鍛錬をしてから芯金と皮鉄を組み合わせてから刀身を作っています。
筆者の考察
古刀に使われる鉄が違う、作られた技法も多分違うと思われます。
折り返し鍛錬で作られているとしたら鉄の組織は均一になる。
叩けば叩くほど組織は均一になるからです。
更に言えば新刀の作り方は簡単に再現できる数打ちの作り方だったのではなかろうか?
江戸時代にそこまで切れる名刀を作る需要が減ったり口伝が上手くいかなかったりして途絶えてしまった可能性は高い
個人的に新刀から失われてしまった技術があったから古刀の方が優れているというわけ
更に断面組織が不均一であるという事は衝撃に強い構造であるとも言える。
いろいろな物質が介在しているから不均一に見えるのではないだろうか?
鉄に含まれる不純物がどう作用したのか?も気になるところだけど
折り返し鍛錬自体も科学的には2回でいいなんて言われています。
つまり、新刀の折り返し鍛錬は刃紋をつけるための作業でしかない。
個人的には折り返し鍛錬の際になんか混ぜてないかと思っています。
もしくはいろいろな鉄を練り合わせて作られたのでなかろうか?
まとめ
古刀は平安時代中期から安土桃山時代後期まで作られた刀の事で江戸時代に作られた新刀とは作り方が違うと考えられている。
日本刀としての性能は新刀よりも古刀の方が優れている。
いろいろな考察や憶測がされているがロストテクノロジーが多いため古刀の再現は出来ていない。
名工たちの口伝が残っていないため、再現は不可能と言われています。
古刀の断面を見ると複雑で不均一な金属組織をしており新刀は金属組織が均一になっている。
この辺りが古刀の切れ味と粘りの秘密ではないだろうか?
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ