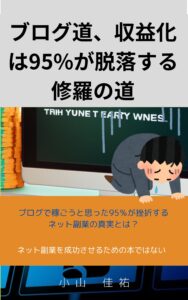料理人に限らず伝統的な職人が一人前になるには10年とか時間をかける事が多い。
ただ、それは無駄じゃないかという意見がある。
確かに技術やノウハウの伝授は言葉で簡単にできる。
だけど、体の使い方はなかなか身につかない。
言葉では表現できない感覚を伝えきるには時間がかかった。
筆者は料理人ではないけど体の使い方というのは結構、重要だと思う。
野菜の皮を剥くにしても体の使い方を覚えないとすぐに疲れてしまう。
先日、たまたま山芋をすり下ろす時に気がついたのですが
腕で山芋をすり下ろすというよりも脇を締めて肩甲骨を動かすようにすり下ろした方が疲れない。
こういう言葉にできないノウハウを教えるのに時間がかかる。
職人の修行期間が長い理由を考察していこうと思います。
無駄だと言われる理由
修行に時間をかけるのは無駄ではないか?
という疑問について考察するに
あるタイミングで身体的なノウハウが失われてしまったのではないだろうか?
大きなターニングポイントは明治時代か第二次世界大戦くらい
この時期に多くの人が亡くなってしまった結果
身体操作が使える人がいなくなった。
こう考えると無駄だと言われる理由が分かります。
先輩や師匠の身体操作を見取り稽古してきた流れがぷっつり切れてしまった。
言葉に出来ない事を覚えるのに時間をかけたというのが本質ではないだろうか?
鍛錬を抜きにしたら
体の使い方や体を鍛えるという部分を教えないというなら
2〜3年の修行でいい。
身体操作や鍛錬は長い時間がかかるけどそれを無視していいなら期間は短い。
江戸時代と現代では事情が違う
そもそも、江戸時代とは事情が違う。
昔は丁稚奉公で10歳前後で働いていたわけだし
そこから10年修行してというならちょうど二十歳でお金も貯まっているから独り立ちできる
そういう感じです。
2〜3年で修行を終わらせてもまだ成長期みたいな子供じゃ使い物にならない。
だから体を鍛えるとか知識をゆっくり身につける事が重要視されたと考察します。
今は高卒とか大卒から修行するから前提条件が違う。
そりゃあ長過ぎる、無駄と感じても仕方のない事。
今は機械で代用出来てしまう
昔は人間がやっていた事も今は機械で出来てしまう。
そう考えると体を鍛える必要性が薄れた。
機械や道具によって修行期間が短くなった。
だから、体の使い方とか体の鍛錬よりもセンスが重視されるようになった。
まとめ
昔の料理人とか職人さんの修行期間が長いのは
- 知識の伝授
- 技術の継承
- 体の使い方を覚えさせる
- 身体作り
- 働き始めた歳が若い
という要素があるからじゃないだろうか?
今はYouTubeやレシピ本などがある。
料理人を志す人が働きに出た時点で包丁の持ち方くらいは覚えている。
江戸時代とかだと、多分包丁の使い方から火の起こし方まで教えないといけない
それに加えて体の使い方も見せながら教えるという形だったんだと思います。
今はある程度、ショートカットできるから無駄だろってなる。
飯炊き3年握り8年なんていうのも薪の火でやるから火加減はこうだ!とは言えなかった。
握り8年というのも力加減を説明できなかった。
現代だと握りはシャリに空気を含ませるように軽く握ってとか
言語化が出来ている。
昔は言葉で説明出来なかったから修行期間が長い。
化学が発達した結果、かなり短縮が出来た。
それと体の使い方という要素が失われてしまったのではないか?
そう考えると修行期間が短縮してしまうのも仕方ない。
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
マインドフルネス(瞑想)のやり方とはどこでもできるリフレッシュ!