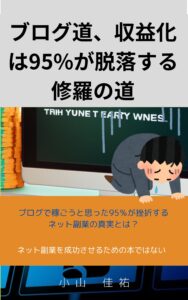米俵の重さは60kgです
現代人の感覚としては結構、重いですね。
しかし、驚くべき事に米俵1俵の重さは
大人が肩にかつげる重さなんだとか
確かに肩にかつげる重さと言えばそうだけど
鍛えてない女性は無理だよな〜という感じ
昔の人はそれくらい楽勝なのかも?
60kgに決まった時代は?
江戸時代は正確な決まりはなく米俵は高さ75cmの直径50cmくらいのもので重さもばらつきがありました。
60kgに統一されたのは明治時代末期だそうです。
米俵1俵は玄米60kg分という事になった。
60kgというのは当時は男女問わず誰でも持ち運べる重さであったという
正直、江戸時代から明治時代の人は体が強すぎる
というよりも体の使い方とか姿勢とかが違っているのかもしれない。
探せば昭和初期の写真とかも見つかる。
重さの単位は
- 1石・・・・150kg
- 一俵・・・・体積約72l 重さ60kg
- 一斗枡・・・体積約18l 重さ15kg
- 一升枡・・・体積約1.8l 重さ約1.5kg
- 一合・・・・体積約0.18l 重さ150g(0.15g)
忍者の体重制限は60kg
忍者の体重は60kg、大体米俵と同じ重さでした、
60kgならば自分の体を扱いやすいからです。
忍者は米俵を使って鍛錬をしていました。
米俵を自在に持ち上げる事が出来れば自分の体も自在に持ち上げる事ができるからです。
天井に張り付いたりするなんて話もあるからちょっと信憑性が生まれるのが面白い
米俵を担いで力比べ盤持ち大会
富山県南砺市の城端地域では江戸時代の頃から行われる奇祭「盤持ち大会」が行われている
重たい米俵を肩に担いでその重さや回数で力比べをする競技だ。
現代でもこのお祭りが続いており45kgの米俵や90kgの米俵を肩に担いぐ
肩に担いだら片手を横に開いたら一回とカウントする。
女仲仕という職業があった
実際に女性が米俵60kgを運んでいたという記録も残っており
女沖仲仕という職業がある船荷を陸揚げして倉庫に詰める仕事をしていた。
米俵を船から降ろして担いで倉庫まで運ぶという仕事をしていた人がいるという話
写真が残っている
写真では女性が米俵を背負って運んでいる。
これが戦前では当たり前だったのだろう。
女性であっても米俵を運ぶ事は出来た
もちろん個人差はあっただろうけど、絶対に無理という感じではなかった。
こういう写真を探していると米俵を5俵担いだ女性の写真とかも見つかるから
現代人とは感覚が違うと思う。
まとめ
一俵の米俵が60kgな理由は大人なら誰でも担げる重さであるから
現代人の感覚からしたら半分の30kgなら誰でも担げるという感じなんだけど
明らかに戦前の人たちは体の使い方が違うように思う。
忍者が体重60kgで米俵を自在に持ち上げる鍛錬をしていたのは合理性の塊だと思います。
確かに60kgの人間が60kgの米俵を自在に動かせれば体を自在に持ち上げる事が出来るという理屈は分かる
そこまで体重を管理していたのがすごい、当時は体重計もなかっただろうし。
現代でも米俵で力比べをしているというのはかなり面白い
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
田んぼの収穫量ってどれくらい? 1ヘクタールだと?思った以上にたくさん採れるwww
ずつ背負って倉庫に運ぶ-300x212.jpg)