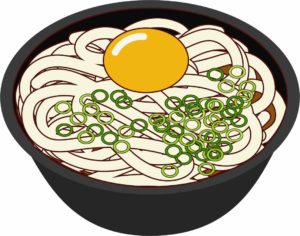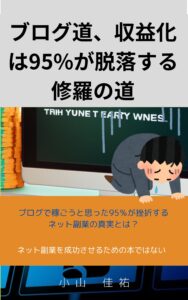そうめんとひやむぎは全く同じに見える
うどんも太さがいろいろあるが何か基準はあるのだろうか?
農林水産省が定めるJAS規格や作り方、それぞれの歴史などを深掘りして紹介していきます。
JAS規格では
JAS規格(日本農林規格)の『乾めん類品質表示基準』では機械で作る干し麺の基準はこのように定めています。
機械乾麺 干し麵の定義
- そうめん→直径1.3mm未満に成形したもの
- ひやむぎ又は「細うどん」→1.3mm以上1.7mm未満
- うどん→1.7mm以上
- きしめん→幅を4.5mm以上とし、かつ、 厚さを2.0mm未満の帯状に成形したもの
そうめんとひやむぎはどっちが太い?
という疑問についてはひやむぎの方が太いですね。
手延べ:干し麺の定義
- 【手延べうどん】→ 長径を1.7mm以上に成形したもの
- 【手延べひやむぎ】又は【手延べそうめん】→ 長径が1.7mm未満に成形したもの
- 【手延べひらめん】、【手延べきしめん】又は【手延べひもかわ】→ 幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2.0mm未満の帯状に成形したもの
規格できっちりきまっているんですね。
ひやむぎはそうめんよりも太い麺なんですね。
うどんの歴史
昭和初期の中国文学者、青木正兒氏(1887年~1964年)は、うどんが日本に伝わったのは奈良時代に中国から伝来した唐菓子〔からくだもの〕の一種の「こんとん」であると主張。
こんとんは餡子の入った小麦粉を練ったお団子を温かい汁に入れたもの
これが進化というか形が変わってうどんになったという説
こんとん(饂飩)から読み方が変わってうどん(饂飩)になったという説です。
うどんの起源はいつ?というのは諸説ある
香川県では讃岐うどんは弘法大師空海が唐の国からうどん作りに適した小麦と製麺技術を伝えたという伝説が残っていますが
遣隋使の時代、つまり空海が唐に行く100年前には伝わっていたという説もあります。
うどんがいつ伝わったのかは定かではない
うどんの作り方
うどんの作り方をざっくり紹介すると
小麦粉に水と塩を適量混ぜて、捏ねて表面が滑らかになったら休ませ
平たく伸ばして切りやすいように折って包丁で切ると麺の形になる。
機械製麺だと
- 機械製麺① 混捏(こんねつ)工程
- 機械製麺② 複合ロール機(足踏み工程)
- 機械製麺③ 熟成工程
- 機械製麺④ 圧延工程
- 機械製麺⑤ 切り出し工程
- 機械製麺⑥ 乾燥工程
やってる事は手延べと同じで生地を捏ねて熟成させて伸ばして切って最後は乾燥させる。
そうめんの歴史
そうめんも思ったよりも歴史が古いようです。
うどんと同じく遣隋使や遣唐使が持ち帰った大陸の食べ物をアレンジした料理
そうめんの発祥の国は?
奈良時代にそうめんの元祖「索餅」が唐の国より日本に伝わりました。
中国の麺で捩じった縄のような形の麺。
もち米の粉をこねて、細くのばして縄のようにねじりあわせたお菓子の一種です。
索餅は別名「麦縄(むぎなわ)」とも呼ばれ、当時はゆでて酢で和えたり、塩味のアズキ汁につけたりして食べていたようです。
これが発展してそうめんになったと言われています。
そうめんは1200年以上前に日本最古の神社、三輪山の大神神社で神の啓示を受けて、疫病退散のために糸状につくった麺が発祥で、そうめんの起源といわれている。
本格的にそうめん作りが始まったのが鎌倉時代
そうめんが普及していったのが鎌倉時代。
室町時代になると「索麺」や「素麺」の文字が使われるようになりました。
主に寺院で暮らす僧侶の間食(てんしん)として作られていたようです。
この時代に現代と同じ作り方や形になったと言われています。
江戸時代
1700年頃、江戸時代ではそうめん作りが盛んに行われていた。
江戸時代に入ると庶民がそうめんを食べるようになった。
江戸時代の文化年間に揖保郡神岡村の森村忠右衛門が阪神地域から素麺製造の新しい技術を持ち帰ってきました。
今でも有名な揖保乃糸は江戸時代から作られていたようです。
「そうめんといえば播州、播州といえばそうめん」と呼ばれるくらい有名に
播州は兵庫県南部を言います。
戦国時代に豊臣秀吉が姫路城へ入った時に播州名産の煮麺の饗応を受けたという話もあり
広まるのは必然だったのでしょう。
そうめんの作り方
そうめんの作り方は揖保乃糸の公式サイトによると
- こね前工程
- 板切工程
- 小より工程
- 掛巻工程
- 小引き工程
- 小分け工程
- 門干し工程
分かりやすくざっくり説明すると
小麦粉と塩と水で生地をこねる、これはうどんと同じ
板切工程はこねた生地を熟成させた後に麺帯状に切る
麺帯を数本まとめてロールで1本にまとめたりする。
この状態だとロープみたいな感じになる。
小より工程は麺帯をねじるように伸ばして直径およそ20mmの麺紐(めんひも)にする。
油を塗りながら熟成させたり伸ばしたりする。
2時間、熟成させて更に細く直径およそ1 2mmにする。
2回目の熟成は1時間して直径6mmにする
3回目の熟成は4時間くらい
掛巻工程は麺紐を、掛巻機(かけばき)という機械でセットする
2本の管に麺紐を八の字にかけて捩りながらかける
セットしたら室箱(おも)と呼ばれる箱に納めて4回目の熟成
熟成は3時間くらい
小引き工程は室箱から出した麺紐を長さ50cmほどに引き伸ばす
天気や気温なども考慮して伸ばしていく
更に道具を使って伸ばして熟成させる
熟成5回目は室箱で15時間
小分け工程は更に1.3mmまで直径を小さくするように伸ばしていく
門干し工程、最後に干して乾麺の完成
ざっくり説明したけどうどんと比べてかなり手間がかかっていますね
うどんと違って麵紐を伸ばしていくのが特徴ですね
そうめんは消化吸収は白かゆと同じくらい
そうめんと白かゆは同じくらいの消化時間で消化できる。
ひやむぎの歴史
そうめんよりも麺の厚みが太く、赤や緑の彩色麺が数本入っている商品もあります。
ひやむぎは室町時代に登場した切麦が起源だと言われています。
切麦を冷やして食べるからひやむぎ、熱々の状態で食べる事をあつむぎと呼びました。
現在ではひやむぎが残った
江戸時代、元禄10年(1697年)の本草書『本朝食鑑』ではうどんは寒い時期に食べるもの、ひやむぎは暑い時期に食べるものと書かれていたりする。
ひやむぎの作り方
ひやむぎも小麦粉と塩と水で捏ねた生地を使います。
うどんと同じように生地を伸ばしてから刃物で細く切ったものをひやむぎと言います
そうめんと同じように手で延ばす手延べひやむぎもある。
ひやむぎに色がついていたりするのは元々、ひやむぎとそうめんを見分けるため
そうめんは丸い麺になりひやむぎは四角い麺になる。
きしめんの歴史
愛知県のソウルフードと呼ばれるきしめんの由来は諸説あるようです。
きしめんの由来は中国のお菓子である「碁石麺(きしめん)」からきているといわれる。
竹筒を切って碁石の型を作りそこに平たく練った小麦粉の生地を抜いて茹でる
きな粉をかけて食べる
名古屋市教育委員会の説明によれば、三河池鯉鮒宿(現知立市)で雉の肉を入れたうどんが好評で雉麺(きしめん)と呼ばれていたという説
きしめんいつできた?かと言うと文献を調べると
きしめんが文献に最初に登場するのは、1838~1853年ごろに書かれた喜田川守貞『類聚近世風俗史』の中の『守貞謾稿』だそうです。
比較的新しい料理みたいです。
ほうとうとの違い
きしめんとほうとうはよく似ているけれど
きしめんの作り方は基本的にうどんと同じで小麦粉と塩と水をこねて生地を作るのに対して
ほうとうは塩を入れずに生地を作る
塩は、小麦粉生地中に形成されたグルテンのネットワークを引き締める働きがあるので、 生地の弾性が増すし、伸展性も少し増す。
きしめんは熟成させる工程があるけどほうとうはすぐに麺にしてしまうなどの違いがある。
まとめ
麺の違いを紹介していったけど
うどんとそうめん、ひやむぎは歴史が古いですね。
そうめんに関しては手間暇がかかりすぎな気がします。
庶民の口に入るようになったのが江戸時代というのも納得
基本的にJAS規格に定められた通りという麺の直径で呼び方が変わるみたいです。
そうめんとひやむぎは中国から伝わった索餅が形を変えたもの
うどんはこんろんというお菓子が形を変えたもの
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
ラーメンの歴史!実は室町時代から食べられていた?あのラーメンが産まれたのはいつ頃か?