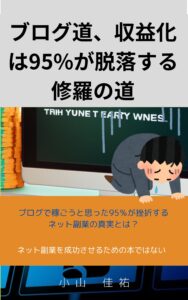武士道とは云うは死ぬ事と見付けたりなんて言葉がありますが
意味がきちんと伝わってなくて玉砕を賛美するような使い方をしてしまいがち
自らの信じるもののために死ぬ事が正義
みたいに使われる事が多いですが間違い




しかし、本来の意味は佐賀藩士 山本常朝が、「葉隠聞書」にこう書いてる。
この記事もおすすめ
五輪書で「踵(きびす)を強くふむべし」とある理由とは?小学生にも分かる解説
原文
「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」として、続きは
【原文】
『二つ二つの場にて、早く死方に片付ばかり也。別に子細なし。胸すわって進む也、図に当らず、犬死などいふ事は、上方風の打ち上りたる武道なるべし。
二 つ二つの場にて、図に当るやうにする事は及ばざる事なり。我人、生る方がすき也。多分すきの方に理が付べし。もし図に外れて、生たらば、腰ぬけ也。此境危 き也。図に外れて死にたらば、気遣いにて恥にはならず。是が武道の丈夫也。毎朝毎夕、改めては死々、常住死身に成て居る時は、武道に自由を得、一生落度な く家職を仕課すべき也。』


意訳
二つのうち一つを選ぶ時、例えば生きるか死ぬかと言った、選択肢があったら死ぬ方を選んだ方がいい。
難しい事ではなく、腹を括って進めばいい
上手くいかない事を考えたり、それでは犬死、失敗を考えるのは上方風の武士道。
自分も他の人も生きるのが好きだ、おそらく好きな方、楽な方にいろいろな理屈をつけて進むだろう。
もし、選択を誤って生き延びる、本当にやるべき事から逃げて生き延びるのは腰抜けである。
思ったように生きるのと思ったようにいかないで生きるのは紙一重の差でしかない。
うまく行かず死んでも「気違い」と言われるだけで恥にはならない、これが武士道の一番大切な事
毎日、朝と夕方に死ぬ覚悟を固めると武士として自在の境地に達して、一生失敗する事がない、家職を全うできる
感想
この言葉が刺さる人はいるんじゃないだろうか?
山本常朝は生きるか死ぬかの選択肢で死ぬ方を選ぶといい葉隠聞書に書いた。
思ったとおりに生きるには死ぬ覚悟が必要
その覚悟さえ決まれば自由に生きられるみたいな事じゃないかと思っています。
現代で当てはまれば明日の不安を理由に転職ができないだとか
思い切った挑戦ができない。
人からバカだキチガイだと言われようとやりたい事に挑戦するには死ぬ気で取り組むしかない。
細かいニュアンスだけど
「死にたい」と「死ぬ気」は違うもの
死にたいという言葉の本質ってゆっくり眠りたいに近い
逆に死ぬ気というのはがむしゃらに頑張る事。
挑戦する事、挑戦する人を上から目線で批判するのは逃げであり
自由に生きたいと思う心に枷をつける事になる。








まとめ
やりたい事、やるべき事があるなら覚悟を固める必要がある。
そういう意味をこめて佐賀藩士 山本常朝は、「葉隠聞書」で
「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」
と書いてるというわけです。
覚悟を決めれば自由に生きられる!
・・・それが一番難しいと思う今日この頃です。