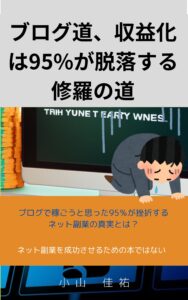草と木は植物だけど、違いを説明してと言われたら説明ができない人もいると思います。
草も木も光合成しながら地面の水や栄養を吸って育つ
草と木の違いは単純に言ってしまえば年輪があるかないかである。
それだけだと木と同じような使われ方をする竹はどうなるんだ?という話にもなるので詳しく解説していこうと思います。
木とは
植物学的に木(木本)と呼ばれ
樹皮の下に形成層が分裂する事で側方、横に大きくなる。
樹皮の下に薄い形成層を作り徐々に太くなっていく。
春から夏の終わりまで形成層が活動し、冬には休眠する。
年輪の太さで年齢が分かったりするのもこのため
種類にもよるがかなり長生き。
現存する大樹で樹齢1000年を超えるものもある。
米国カリフォルニア州インヨー国立森林公園内のブリッスルコーンパイン(日本名はマツ科のイガゴヨウ)といわれます。樹齢は推定4800年
アジア最古のイトスギで、樹齢4000年~4500年。
ちなみに高くなる木は寿命が長く、低い木は寿命が短い。
- 落葉低木であるタラノキ(ウコギ科)は10年
- 常緑低木のジンチョウゲは20~30年。
- カキ、モモ、クリは約50年。
- シラカバが約70年
- ミズキやコナラが約80年。
- トチノキは150~200年
思ったよりも短命な木が多い
とは言っても動物と比べたら基本的に長生きか
柿は高さ2~5m モモは2~4m クリは3~4m
シラカバは高さ20~25m
ミズキは10~15mでコナラは30mくらい育つ
トチノキは高さ35m以上になる。
こうやってみると高く伸びる木は長生きという事が分かりますね。
草本とは?
木本とは違い形成層がない。
ある程度、成長すると茎が太くならなる。
茎とは木の幹に相当する部分のこと。
木と比べると寿命が短く一年で成長し枯れてしまう一年草
一年で成長し二年目で枯れてしまう二年草、
二年以上の寿命がある多年草
宿根草は苦手な季節には根っこなどを残しておくと枯れてしまうが季節が変わればまた生えてくる。
樹木と比べると寿命が短く命のサイクルが早い印象。
草でも結構、大きくなるものでバナナは草になる果物です。
竹は?
世界一成長が早い植物と言われる竹ですが
竹は木?草?どちらなのでしょうか?
成長が盛んな時期には1日、1m以上も成長するという他の植物と比較してもバカバカしくなる成長具合。
林野庁によると1日(24時間)にマダケで121cm、モウソウチクで119cm伸びたという記録があります。
高くなれば10~20mほどになります。
竹の寿命は20年と言われています。
竹には形成層がなく空洞で節がある、それだけだと草のような分類になりますが
しかし、竹を切って中を製品にすると分かりますが木のような材質をしています。
一応、植物学的には竹は木本に分類される。
竹博士として知られる上田弘一郎京大名誉教授によると
「竹は木のようで木ではなく、草のようで草でなく、竹は竹だ」
と言っています。
木と草と竹は違う物といった感じですね。
植物学的には気と木さも竹も本質的には違わないというのが結論らしい。
まとめ
木と草の違いは形成層を作るか作らないかによる違い。
3mにもなるバナナの草も形成層がないから草です。
木は高くなればなるほど長生きです。
草は短く小さいためか寿命が短い
竹は形成層を作らないが木という分類。
ただ、木、草、竹という分け方にした方がいいのでは?という話を竹博士がしていた。
- 木は年輪を作る
- 草は年輪を作らない
- 竹は年輪を作らないが木(例外)
竹は例外だと覚えておけばOK
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
剪定と伐採の違いとは?これだけは知っておかないと恥をかく?意外と歴史は浅くてびっくり古代からある技術でもないんだな~