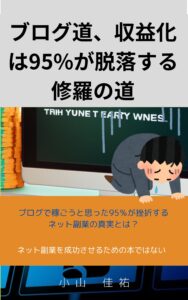お味噌汁やお鍋にうどんや蕎麦、煮付けやおでん、おひたしなどなど
これらに共通するのはなんだと思いますか?
答えは和食によく使われる出汁。
日本人なら1日一度は口にしている出汁
どうして出汁を使うと料理が美味しくなるのか?
出汁にはどんな種類があるのか、それぞれどんな食材から作られているのか?
知っている人は意外と少ないんじゃなかろうか?
今回はそんな【出汁】の秘密を探っていこうと思う。
出汁とは?
だしは漢字で出汁と書く、これはだし汁の事で昆布や鰹節を煮出して料理を美味しくする汁の事を言う。
和食の【出汁】に対して洋食では【フォン】や【ブイヨン】がある。
中華料理屋では【湯(たん)】というものがある。
動物性、植物性の様々な食材が使われている。
ところで和食の出汁は洋食のフォン・ブイヨン、中華料理屋の湯に比べると
ずいぶんアッサリした味わいで香りも上品なものが多い印象。
その理由はそれぞれの食材が関係している。
西洋料理や中華料理屋は食材が肉中心なのに対して日本では魚介類や野菜類など様々な食材が使われてきたの
だから日本の出汁はアッサリしていて素材そのもの良さを引き出す特徴がある。
っと言われているんだ。
日本の出汁、その歴史は?
日本での出汁は歴史が古くなんと縄文時代から出汁が使われていた。
この時代には野草や木の実、肉や魚を煮るという技術が生まれ
その中でも魚や肉の煮汁が【食べ物を美味しくする】って気づいたらしい。
これが現代につながる出汁の起源だと言われているんだ。
そして7~8世紀にはかつおや昆布が出汁として使われるようになり(※古事記以前の書物ってないから時代が飛んでしまうのは仕方ない。)
戦国時代から江戸時代のはじめには現在と同じような鰹節が使われるようになったと言われているの
同時にこの頃は物流も発達していたから昆布や煮干も全国に伝わった
出汁は本当に昔から日本人の食文化に密接に関わってきた。
出汁が美味しいと感じる理由
出汁を美味しいと感じる理由は
出汁に含まれる「うま味成分」のためなんだけどこのうま味成分が発見されたの1900年代になってから
つまり、ごく最近になってから
- カツオなどに含まれる「イノシン酸」
- 昆布などに含まれる「グルタミン酸」
- 椎茸などに含まれる「グアニル酸」
この代表的な3つの旨味成分を日本人が発見し
それまで甘味、塩味、酸味、苦味の4つしか知られていなかった味に5つ目の味「うまみ」が加わったんだ。
今では「umami」として世界に広まり、世界中のシェフや美食家が注目する世界共通語になった。
和食出汁の種類
日本の出汁にはどんなものがあるのか?
詳しく見ていこうと思う。
日本料理において出汁(だし)は重要な役割を担っており、様々な種類があります。代表的な出汁の種類を以下に紹介します。
- かつお節出汁(かつおだし):かつお節から取った出汁で、醤油や味噌などの味噌汁やうどん、そば、天ぷらのつゆなどによく使われます。
- 昆布出汁(こんぶだし):昆布から取った出汁で、お吸い物やお鍋、煮物によく使われます。
- しいたけ出汁(しいたけだし):干ししいたけから取った出汁で、炊き込みご飯や鍋物によく使われます。
- 鰹節と昆布のだし(かつおこんぶだし):かつお節と昆布を合わせた出汁で、一般的な和風料理によく使われます。
- 精進出汁(しょうじんだし):昆布としいたけを合わせた出汁で精進料理に使われる
- 鶏がら出汁(とりがらだし):鶏の骨から取った出汁で、鶏そぼろや鶏飯、鍋物などによく使われます。
- 豚骨出汁:とんこつラーメンの出汁は、主に豚の骨や肉、野菜、魚介類などから取ります。骨からはカルシウムやコラーゲンなどが抽出され、コクや旨味の源となります。
これらの出汁は、それぞれに特徴があり、料理の種類や味わいに合わせて使い分けることが重要です。また、出汁は料理に深みやコクを与えるため、素材の質や取り方にもこだわることが大切です。
1つ目、鰹出汁
和食の出汁といえばやはり鰹節が筆頭に挙げられるね
鰹節はクセが少なくて味も香りも上品な出汁が取れるのでいろいろな料理に使われているんだ。
代表的な産地は鹿児島県の枕崎と山川、静岡県の焼津などだよ
ところで鰹節の【節】ってどんな意味だと知ってる?
これは鰹節を作るためには水揚げしたカツオを三枚におろさなきゃいけないんだけど
この「おろした身の1つ分」を節というんだ。
鰹節を作る工程は
- 水揚げしたカツオを三枚におろして節を作る
- 節を75~98℃のお湯で60~90分かけてじっくり煮る
- 身を傷つけないように骨を取る(手作業)
- 薪で何回も燻して水分を抜く
- 「かつおぶしかび」をつけて発酵させる
- 戸外に広げたムシロの上で「節」を並べて天日干しする。
大雑把に説明するとこんな感じです。
注目すべき5番目の手順、鰹節はカビを利用して発酵させたもの
つまり、納豆やヨーグルトなどの発酵食品の仲間ってことになる。
これだけの工程にかかる日数は約4ヶ月くらい
ただ「、鰹節には「荒節」と「本枯節」の2種類があり
本枯節と呼ばれるものだけが発酵食品に分類される。
荒節はカツオを茹でて燻して乾燥させたもの本枯節と違って2週間から20日で完成する。
原料のところに「かつおかれふし」と書いてあるのが「本枯節」
鰹節と書かれているものは荒節なんだよ。
花かつおは荒節を削ったものを言います。
鰹節に含まれる主な旨味成分は「イノシン酸」という成分
イノシン酸には細胞を活性化させる働きがある。
と言われている。
また、タンパク質やお肌にハリや潤いを与える。
「メチオニン」という成分が含まれているので美肌効果や脳の発達にも効果が期待できる。
更に疲労回復に役立つ、ビタミンB1・B12やミネラル類も多く含まれている。
鰹出汁は昆布だしよりも味がはっきりしていて短時間で出汁が取れるから初心者にもおすすめ
どんな料理にもよく合う万能の出汁だけど
特にうどんや蕎麦のつゆ、お味噌汁など汁物に適しているんだ。
2つ目 昆布だし
2つ目は昆布だし、鰹節と並んでよく使われる出汁です。
7月中句から9月末にかけて採取された昆布は海水できれいに洗浄して汚れを取り除いた後
十分に乾燥させてから出荷する。
昆布の種類は40種類以上あるんだけど
実際に「出汁」として流通しているのは主に
- 利尻昆布
- 日高昆布
- 真昆布
- 羅臼昆布
この4つになる。
透き通った上品な出汁が取れる利尻昆布は京都の懐石料理などに欠かせない高級昆布の一つ
繊維質が柔らかい日高昆布は出汁以外にも昆布巻きや佃煮にも利用されていて主に関東以北で使われています。
そして上品な甘みがある真昆布は関西地方で濃いコクがある羅臼昆布は北陸地方でよく使われている。
昆布にはグルタミン酸という旨味成分が含まれていて脳の神経伝達物質になったりリラックス効果のある「GABA」の材料になったりアンモニアを解毒して尿を出やすくする働きがある。
更に美肌や血圧抑制など美容や健康にも効果があると言われているんだ。
上品で優しい味わいの昆布だしは炊き込みご飯や煮物など素材の味を大切にする料理とよく合う
3つ目は合わせ出汁
合わせ出汁とは鰹出汁と昆布だしを合わせたもの
イノシン酸とグルタミン酸を合わせると相乗効果で旨味がグンッと増す
味が濃厚で香り高いのでめんつゆやお吸い物、茶碗蒸しなどがおすすめ
4つ目は煮干出汁
煮干しとは読んで字の如く魚を煮て干したもの
関西では「いりこ」と呼ばれたりもする。
煮干しとして使われる魚はカタクチイワシが一般的だけど
ウルメイワシやマイワシ、アジやサバなどの煮干しもある。
カタクチイワシにはイノシン酸とグルタミン酸の両方が含まれている。
旨味成分の相乗効果で料理が一段と美味しくなる
魚の香りと味が比較的強いのでお味噌汁に使われる事が多い
他にも鍋料理やラーメンなど幅広い料理に使われています。
5つ目はアゴ出汁
アゴ出汁はあご(トビウオ)を焼いて乾燥させたもの。
煮干しに比べて臭みがなくあっさりして上品な出汁が取れる
6つ目は干し椎茸
干した椎茸にはグアニル酸という旨味成分が含まれている。
他にも胎児の成長に必要な葉酸や骨粗鬆症の予防になるビタミンD
血圧を抑えるエリタデニンという成分が含まれていてこれらの成分は戻し汁にも含まれている。
だから干し椎茸の戻し汁も捨てずに出汁としてそのまま使う。
煮物や味噌汁、茶碗蒸しにつけ汁など様々な料理に使えます。
7つ目は精進出汁
精進出汁(しょうじんだし)は、菜食主義者や仏教徒が用いる、動物性の食材を使用しない出汁のことを指します。
主に昆布や干し椎茸、植物性の調味料を使って作られます。
昆布は、うま味成分のグルタミン酸を豊富に含み、椎茸にも同様のうま味成分が含まれています。
また、植物性の調味料としては、醤油やみりん、塩、味噌、梅干しなどが用いられます。
精進出汁は、軽い口当たりであることが特徴で、あっさりした味わいが特徴です。
主に、精進料理やお寺の食事、また健康や美容に関心がある方などにも人気があります。
ただし、植物性の出汁であるため、旨味やコクは動物性の出汁に比べるとやや劣る場合があるため、調味料の配合や素材の選択には工夫が必要です。
その他の出汁
甘みのあるグリシン酸を含むエビやカニ
旨味成分のコハク酸を含むあさり、しじみ、ホタテなどの貝類
アミノ酸やイノシン酸が豊富な鶏・牛・豚などの肉類
肉や魚の臭みを消したり隠し味として使われる野菜類なども出汁として使われる。
魚の骨や動物の骨などで出汁を取っている。
出汁のとり方の種類
いろいろな出汁がある事は分かったと思うけど
出汁の取り方には一番出汁と二番出汁がある。
一番出汁は文字通り、その素材から最初に取った出汁の事
香りが強く、色が綺麗で上品な味わいが特徴
だから出汁が主役になるお吸い物やお雑煮、茶碗蒸し・雑炊のような比較的味の薄い料理に使うのがおすすめ
一方、二番だしは一番出汁を作った出し殻を再利用してとった出汁の事
色はややくすんでいて香りもあまり残っていないけど旨味が凝縮されている。
だからお味噌汁や煮物みたいな味の濃い料理に使うんだって
商品としての種類
商品として販売される時は
- 乾物だし
- だしパック
- 顆粒だし
この3つがある。
この違いが何かというと
乾物だしはいわゆる天然だしの事で鰹節や昆布に煮干し、干し椎茸などの乾物を水につけたり煮出したりして作る出汁の事
本格的で味もよく食材本来の栄養素やアミノ酸が摂れるメリットがある一方、とにかく手間と時間がかかる。
1℃作った出汁は長期保存できないというデメリットがある。
だしパックは天然素材を粉末上にして袋に詰めたもの
そのままお湯に入れるだけでお出汁が取れる終わったら袋を捨てるだけという便利なものです。
これなら本格的な出汁が簡単に取れるし食材本来の栄養素やアミノ酸もしっかり取れる。
一般的に100%天然の食材を使っている出汁パックは値段が高めです。
あまりに値段が安いものは天然と言っても添加物が混ざっている事もある。
天然にこだわるなら原材料はしっかり確認しよう。
最後に顆粒だし、顆粒だしは名前の通り粒や粉の状態のだしの素のこと
さっとお湯に混ぜるだけで簡単に出汁が取れる便利な代物だけど
顆粒だしには実は2種類ある。
1つ目は原材料の主成分が鰹節や煮干しの粉末でこれに調味料を加えて味付けてした顆粒だし
2つ目は原材料が塩や砂糖で素材やエキスで味付けした風味調味料と呼ばれるもの
風味調味料は手軽で簡単、長期保存が可能というメリットがある反面、塩分や化学調味料がプラスされているものも多いというデメリットがある
食品の原材料には使用量が多いものから表示しなければならないというのがあるのでそれを見れば分かるんだけど食塩や砂糖で始まるものが多い
手軽で美味しいけど塩分のとりすぎには気をつけましょう。
液体だし
最後は液体だし、出汁にはもう一つ、液体だしというのがあって
液状の出汁に醤油やみりんで味付けしたものを言います。
そのまま煮物やめんつゆとして使えるので料理初心者でも手軽に美味しい料理が作れてるからおすすめ
ただし、液体ダシの中には添加物が含まれているものあるし塩分の摂りすぎにならないように注意が必要
まとめ
今回の記事でダシについてよく分かったと思います。
この記事を参考に自分の生活スタイルにあった出汁を探してみるのも面白いかもしれません。
毎日、何気なく口にしている出汁だけど知らなかった事もあるんじゃないでしょうか?
それぞれに特徴がありメリット・デメリットがあるので用途によって使い分けると良いと思うよ
この機会に是非、自分の生活に合う出汁を探してみてくださいね
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ