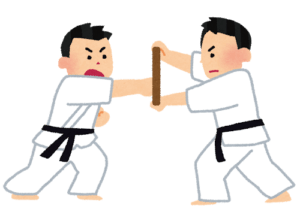空手の目指す理想は一撃必殺みたいな風に言われますが現実ではそうじゃない
格闘技という競技の空手では一撃必殺は無理という意見もある。
だが、空手が一撃必殺を唱えたのはその方が強いからではない。
思いつきで目指したわけではないと思われる。
格闘技としての空手で一撃必殺は無理だろうけど武道の空手は手首から先の変化で目突きや一本拳、手刀に抜手など急所を刺す攻撃方法のバリエーションがすごい。
空手の歴史
空手は琉球王国、現在の沖縄で生まれた武道でその始まりは謎に包まれています。
二つの説があり
- 1392年に明から那覇に移住してきた「?(ビン)人三十六姓」と呼ばれる人々が琉球に移住し中国拳法を広めた結果、空手になった。
- もう一つの説は琉球の伝統的な舞踊である【舞方】から生まれた「手(ティー)」が「唐手(空手)」に発展したという説です。
とりあえず、14世紀頃にはあったと解釈しましょう。
琉球の歴史を簡単に江戸幕府に
琉球の仮想敵は薩摩藩である。
これは歴史的な背景を見ても間違いない。
14世紀に三山時代と呼ばれる時代が終わり琉球王国は統一された。
16世紀末には豊臣秀吉から朝鮮出兵のために食糧提供を義務付けられた。
琉球王国と言いつつも日本だったのがわかる。
ただ、地理的に民にも近いため朝鮮出兵の情報を民に流していた。
そんな琉球だけど、1609年、徳川家康の許可をもらった島津氏が琉球を支配した。
琉球は薩摩島津氏に従属しつつ中国と朝貢貿易をしている状態だった。
16世紀からの琉球は薩摩藩が支配していた。
薩摩武士が仮想敵
琉球では14世紀の尚 真王が武器禁止令を出しており、16世紀、薩摩藩でも武器禁止令が出されている。
いわゆる刀狩りというやつです。
武器の携帯、つまり日本刀などの携帯が認められていなかったため。
素手や身近にある物で戦う技術が磨かれていった。
少なくとも16世紀、琉球の人々が倒すべき相手は薩摩藩、薩摩武士だった。
彼らの扱う示現流、薬丸自顕流は一撃必殺を体現した剣術であり。
空手も一撃必殺にならざる負えない。
というのも示現流の豪剣をかわす、または先手の攻撃で相手を戦闘不能にしないと確実に斬り殺されるからだ。
戦場で武器を失っても戦えるように発展した柔術とは違い、相手が日本刀を持っているのに対してこちらは素手という状況で発展したのが空手
圧倒的に不利な状況で長く戦えないという想定で作られたのが空手。
18世紀の琉球王国時代、松村宗棍と言う人が薩摩に渡って示現流を学んでいた。
巻き藁で正拳突きをするのは示現流の影響ではないかと言われている。
まとめ
武道、武術のスタイルは仮想敵によって大きく変わる。
特に素手の武道は圧倒的に不利な状況であるため独自の進化がある。
空手が中国拳法の太極拳みたいに体の一部に触れて動きを感じ取る聴勁などの技術が発達しないのは
日本刀を操る武士が相手だったから。
中国の武器が長柄のゴツい槍とかだから超接近戦が有効だっんだろうな〜
あくまでも考察だけど、武道というのは戦う相手とか状況によって進化するもの。
なので歴史を調べるといろいろ面白い
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
生卵を飲むシーンが映画【ロッキー】にあったけど当時のアメリカ人の反応が日本人と違う件
目玉焼きの焼き方を7種類、紹介!!あなたはどれだけ知っている?