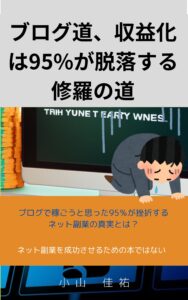居酒屋さんとかで店員さんがしている前掛け。
魚屋のおっちゃんや八百屋のおっちゃんもつけていたりします。
日本で昔からある商売のユニフォームみたいなイメージがありますよね。
前掛けと似たようなものでエプロンがあります。
エプロンと前掛けの違いとは?
エプロンも前掛けも同じじゃん!と思われるかもしれませんがエプロンと同じような機能を持っているのは割烹着の方。
前掛けもエプロンも英語にするとapronになります。
同じ物として扱われがちですが全く違う物です。
前掛けとエプロンの違い
前掛けもエプロンも作業着で汚れがつかないようにするためのものです。
大きな違いはエプロンが首から下げて使うのに対して前掛けは腰に巻く。
前掛けは腰に巻く四角い布
エプロンは首から下げ腰でも紐で固定して服が汚れないようにするもの
前掛けは下半身の汚れなどが服につかないようなデザインになっているのに対して
エプロンは上半身と下半身両方に汚れがつかないようなデザインになっている。
エプロンも腰に巻くタイプはあるんだけど前掛けほど紐がしっかりしていない。
前掛けは腰痛防止のコルセットとしての機能もあったわけだからそこが大きな違い。
エプロンは服が汚れないように進化したのに対して前掛けは汚れない事も大事だけど腰をしっかり締める事に重点が置かれているのかも?
元々が袴を着ていない時に締める物だったみたいだから服が傷まない事もそうだけど
やっぱり腰を紐で締める事が目的だったのではなかろうか?
エプロンは服に汚れがつかないように
エプロンは服が汚れないように身につけるものです。
上半身から下半身までしっかりガードしています。
料理するときなど油がはねたりするし掃除する時も服に汚れがつかない。
元々は古代エジプトが発祥でおしゃれ用の衣服だった。
壁画に書かれているのは腰から三角形の布をぶら下げている男性でした。
中世ヨーロッパでは聖職者や上流階級のご婦人が豪華な飾りのエプロンを身につけていたそうです。
現在、使われるような実務用のエプロンも近代に近づくにつれて開発されていきました。
今のエプロンは実務用ですね。
前掛け
前掛けをつける意味として
- 腰痛防止
- 肩や衣服を守る
この二つです。
前掛けは酒屋や米屋・魚屋・八百屋などの比較的重いものや割れ物を扱う業種でよく使われていました。
エプロンと比較すると生地が厚いものを使っている。
腰に紐を巻いてしっかりと締めるのでコルセットのような役割を果たして腰への負担が軽くなるというわけです。
前掛けの位置はベルトと同じかそれよりも少し下の辺りにつけます。
ちょうど丹田と呼ばれて位置
肩や衣服を守るというのは物を運ぶ時にズボンが破けたりしないようにするというのは分かりますが
肩?
昔は木箱なんかを肩に当てて運んでいました。
その時に前掛けを肩にかけて衣服と肩を守っていたみたいです。
後は軽く手を拭ったりするのにも使われています。
明治時代くらいから前掛けに屋号を入れてユニフォームとしても使われています。
前掛けは諸説あるようですが室町時代頃に日本で産まれたものとされています。
まとめ
前掛けは室町時代に生まれた作業着で衣服が汚れたり破けたりしないようにするためと腰痛防止のために作られた。
エプロンは古代エジプトの壁画にも描かれるくらい古くからある。
最初はおしゃれアイテムだったけど
服が汚れないように今の実務用エプロンが作られた。
大きな違いはエプロンは汚れ防止や服が破れたりしないようにするのが目的
前掛けも汚れ防止や服が破れないためと腰痛防止のために作られた。
和服って大体が腰を紐で締める。
腰が入ってる感覚が分かりにくいから腰を締める物を好んだのかもしれません(個人の感想)
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
腹筋は99%の人が力の入れ方をわからないでいる!お腹が使えると革命的