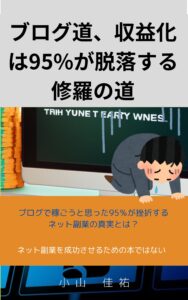日本刀と言えば日本の伝統的な武器です。
その歴史は非常に古く
日本刀の成立は平安時代中期頃です。
古墳時代から日本刀が生まれるまで上古時代の刀は太刀(たち)と表記され
上古刀と区分されます。
上古刀として、「三種の神器」のひとつである「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ)別名「草薙剣」や、「七星剣」(しちせいけん)などが有名です。
日本最初期の刀剣は両刃(もろは)で反りがない剣
もしくは反りのない直刀でした
打撃を与えたり刺突が目的の武器で斬る事が重視した日本刀とは違ったものです。
これが蝦夷征伐を経て平安時代には日本刀となった
蕨手刀が起源?
古墳時代頃(6世紀)に東北地方に住んでいた蝦夷との闘いが盛んになり
そんな蝦夷の人々は馬に乗り刀を使う戦闘スタイルでした。
彼らが使っていた刀が蕨手刀と言われ蕨のように柄が湾曲した刀でした。
馬に乗った状態では湾曲した刀が猛威を振るったため
その技術を吸収して
蕨手刀から毛抜形蕨手刀、そして毛抜形太刀に進化して
日本刀になった
毛抜形蕨手刀とは柄の部分が衝撃を逃がすために肉抜きされているもの
毛抜形太刀も同じく柄の部分が肉抜きされている。
それを大和朝廷が手に入れ改良したのが日本刀になります。
蕨手刀と唐から伝わってきた唐太刀の技術が組み合わされてものだと思います。
たたら製鉄はヒッタイト由来?
日本刀と言えばたたら製鉄で作った玉鋼で作られています。
そんなたたら製鉄はヒッタイトが由来なんだとか
ヒッタイトといえば古代のトルコで栄えた帝国だが
そのヒッタイトでは砂鉄から製鉄するたたら製鉄が行われていたようだ
たたら製鉄は古墳時代、日本に伝わったという説がある。
ヨーロッパやアジアにも技術は拡散したようなのだが日本以外では残らなかったようです。
唐の太刀と蕨手刀のミックスでは?
蕨手刀だけではなく拵えなどは唐太刀の影響も受けていると思われる。
唐太刀は直刀だが日本刀ができる前は武将が腰に差しているのは唐太刀だった。
坂上田村麻呂も黒漆剣という直刀を使っていたようだし
毛抜形蕨手刀から毛抜形太刀に刀身が伸びたのも唐太刀の影響だろう。
蕨手刀は確かに影響を受けた事は間違いないが
それだけではなく当時の最先端技術を結集して作り出したのが日本刀
蕨手刀の鉄は炭素が低くあまり硬くない鉄だったそうです。
これは憶測ですが遣隋使や遣唐使の段階で優れた製鉄技術を学んできていた朝廷が
同じ形の武器を使わせたら素材の強さで勝てるよなと思ったり
最初期の日本刀である小烏丸は先端部分が両刃になっている珍しい作りが
今までの剣との転換期っぽくて面白い
湾曲した日本刀になったのは?
湾曲した刀が生まれたのは10世紀頃
一般的に10世紀前半の平将門と藤原純友の乱(承平・天慶の乱)以降とみられています。
それまでの刀を上古刀と呼びそれ以降を古刀と呼んでいます。
その後、発展していきました。
鎌倉時代が最盛期と言われています。
砂鉄の豊富な地域に鍛冶師が集まり五カ伝になった
- 「大和伝」(奈良県)
- 「山城伝」(京都府)
- 「備前伝」(岡山県)
- 「相州伝」(神奈川県)
- 「美濃伝」(岐阜県)
まとめ
日本刀の起源は蝦夷征伐の時に蝦夷が使っていた蕨手刀をベースに
唐太刀などの技術やヒッタイトから伝わった、たたら製鉄などの技術を組み合わせて作られた
毛抜形太刀から日本刀に進化した時に拵えが唐太刀に影響されたのだろう。
平安時代中期には日本刀の原型が産まれて今に続いているというわけです。
日本刀というのはいろいろな技術を貪欲に組み合わせた結果、生まれた武器だったようですね。
この記事もおすすめ
日本刀は戦場では使われなかったのか?根本的な勘違いはあると思う。
大太刀と長巻って?日本刀は戦場ではサブウェポンだったというのは間違い