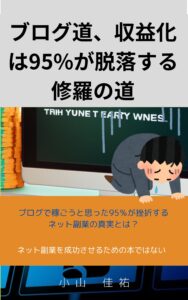日本刀には打刀や太刀、大太刀、野太刀などと呼ばれる日本刀があるが
南北朝時代から戦国時代にかけて槍が登場した事によって日本刀はサブウェポンとして扱われた。
これは半分本当で半分嘘です。
一般的な日本刀では平野のような場所で戦うのに相応しくない。
槍が登場したのなら日本刀はサブウェポン、乱戦の時にしか使えない武器になってしまうのは分かる。
広い場所での合戦がメインの戦国時代
弓や槍、火縄銃が主力ではあったけど
日本刀も合戦仕様のものがありました。
大太刀・野太刀
大太刀・野太刀は同じ日本刀で呼び方が違うのですが基本的に刀身が長い刀です。
打刀が一般的に刀身が75cmで全長は90cmほど
大太刀は刀身が90cm以上のもの全長は1.2〜1.5mはありました。
騎馬に乗った武者が使った武器だったのです。
馬上から馬のスピードを活かして振り下ろす。
そんな使い方をしていました。
歩兵が槍や薙刀を持つようになり騎馬での一騎打ちや馬上で大太刀を振るうという戦闘スタイルは難しくなった。
大太刀は歩兵が使うと扱いにくいというか柄が短いため手首に負担がかかるようになるため
大太刀を扱いやすくする発展があった。
振り回し易いように刀身の鍔元から中程の部分に太糸や革紐を巻き締めたものが作られるようになった。
それを「中巻拵えの野太刀」、「中巻野太刀」となり、単に「中巻」と呼ぶ
根本、鍔の方は刃をつけずに皮を巻いたのが中巻
それを更に発展させたのが次に紹介する。
長巻
単純に大太刀の柄を長くしたもの
刀身と同じくらいの長さにした柄を使えば長い刀身を歩兵でも使える。
この長巻ですが戦国時代にも活躍しており
上杉謙信を始め戦国末期の豊臣秀吉さえ自軍に長巻隊を
持っていたとされ接近戦においては最強の武器とされております。
馬上での戦闘はもちろん、歩兵の武器としても強い武器だった。
戦国時代にメインウェポンとして使われた日本刀は長巻だったというわけです。
かなり練習して習熟しないと自分の馬を傷つけてしまうなんて事もあった。
長巻は薙刀とか槍に近いんじゃないかと思われがちですが
単純に日本刀を延長したものだから体の使い方は剣術と同じだったのではないだろうか?
全くの素人意見だけど柄を持つ位置によって槍や薙刀のようにも使えたし短く持って日本刀のようにも使えたのではないだろうか?
江戸時代の平和な時代には不要なため使われなくなったし
幕末は室内や狭い路地などの戦闘になり長巻がメインにはならなかった。
You Tubeに動画があったので掲載します。
やはり突くとうよりも日本刀的な斬る使い方ですね。
柄の持ち方で間合いを変えながら斬りかかるみたいな使い方をされると怖いな~
日本の武道って何かしら残っているから調べるのが楽。
騎馬に乗っている状態ならこっちの方が扱いやすそう。
脇の下に柄を固定できるのはかなり扱いやすそう。
長巻直し
長巻を基にして刀に作り直したもの
江戸時代に長巻直し(ながまきなおし)として多く作られた。
3尺(約90cm)の大太刀を打刀の長さ二尺(約60cm)の脇差があるが
江戸時代は3尺以上の刀を持ってはいけなかったので刀身が二尺八寸以下の打刀や太刀に打ち直された。
基になった長巻の形状から
鳥居反り(中反り)
ほとんど反りを持たない「無反り」で「鵜の首造り」や「冠落造り」という形の物が多い
同じように薙刀を日本刀に直した薙刀直しなどもある。
戦のない江戸時代、長巻は打ち直して携帯できる打刀に擦り上げられた。
後、長巻直し造りといって長巻直し風の打刀なんかもあったみたいです。
まとめ
日本刀が戦場じゃサブウェポンというのは半分ウソで本当は大太刀の柄を刀身と同じくらい長くした長巻が使われた。
上杉謙信とか豊臣秀吉が長巻隊を作っていたし
九州最強の部隊と恐れられた豊後大友家の立花(戸次)道雪の無敵親衛隊などでは、道雪の輿を中心に置いて周辺を長巻装備の部隊で固めて突撃していたといいます。
修練すればかなり強かったけど、やはりそこまで修練のいらなかった槍の方が主流になったのだと思います。
江戸時代に役目を終えた長巻は打刀に磨りあげられた。
長巻を見た印象だけどモンハンの太刀を刀身を少し短くしたら長巻になるよなと思いつつ
刀身と柄が同じ長さというのはやはり特殊な武器になるのかも?
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
日本刀の雑学記事まとめ、記事にしてほしい事がありましたらコメント欄に書いてください。