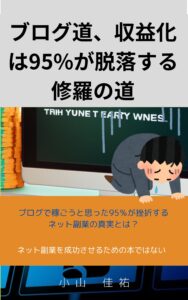水道水が出てくる管の口を蛇口と言いますが
なぜ蛇口なのか知っていますか?
最初は獅子だったってご存知でしょうか。
明治時代に西洋の水道設備が導入されました。
一家に一つ、水道が通っているわけではなく共用栓というもので
みんな共有する水道でした。
共用栓の吐水口は最初ライオンだった
ヨーロッパから輸入した共用栓はライオンのレリーフが彫られたものでした。
ただ、水とライオンという組み合わせがあまり日本人には馴染まなかったようです。
今でも横浜開港資料館の中庭にもあるそうです。
他にもライオンがモチーフの共用栓は残っています。
ライオンではなく別のモチーフを使おうとなって次のような形になりました。
水と言えば龍だろう→龍口
ライオンでは馴染まないという事と水の神様と言えば龍だろうと
龍のレリーフを彫った共用栓が作られたというわけです。
ただし、龍口というのがあまり舌に馴染まなかったようで
【りゅうくち】【たつくち】なのか
やっぱり言いにくい上に龍と蛇は混同されがちだったので
龍ではなく蛇になったというわけです。
龍口が完全になくなったかと言えば
龍の口から水が出る設備は神社の手水舎なんかに残っています。
神社の手水舎には龍が水を出している物が多いのはそういう事なのでしょう。
なぜ蛇口と言うのか?諸説あり
一つの説を紹介しましたが3つほど説があるようです。
- 共用栓にライオンが彫られていた、それを龍に改良しやがて同じ水の神様である蛇と混同されて蛇口になった
- 共用栓の鉄柱を蛇腹と呼んだから水が出てくる部分は蛇口
- 龍の共用栓を蛇体鉄柱式共用栓と呼び略して蛇口になった。
1:ライオンが彫られていたのを龍にしていたが同じ水の神様である蛇と混同され蛇口と呼ばれるようになった
2:共用栓の形が蛇のお腹に似ているから蛇腹と呼ばれじゃあ水が出てくる部分は蛇口だねという感じです。
3:イギリスから輸入した共用栓はライオンが彫られていた、
れを龍に改良したが龍の元となった生き物が「へび」であることから、
「蛇体鉄柱式共用栓」と呼ばれようになり専用栓が付くようになった時それを略して蛇口になった
まとめ
明治時代に西洋の水道設備を輸入して日本独自に作り変える段階で
ライオンは龍になって、龍から連想して蛇、蛇口になった
もしくは丸い共用栓が蛇腹に見えたという説もあったりしますが
個人的には龍と蛇、混同して蛇口になったというのが面白い
龍口の方も神社には残っていたりするから無くなったわけじゃない
日本の水道には
- ライオンの顔から水が出るタイプ
- 龍の口から水が出るタイプ
- 蛇口から水が出るタイプ
この3つがある。
基本的に蛇口が一番メジャーになっているというわけですね
ではでは(^ω^)ノシ