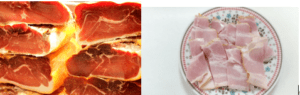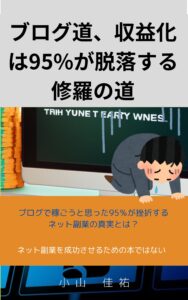意外と説明できない身近なものにハムのベーコンの違いがあるのではないでしょうか?
ベーコンは燻して作るもの、ハムは燻製してから茹でたりして作るようです。
ベーコンもハムも似たような感じに見えてしまうからざっくりとした説明をしがち
今回はそんなハムとベーコンの違いについて紹介します。
ベーコンとハムの違いって?
ベーコンとハムはどちらも豚肉を加工した食材ですが、製法や風味に違いがあります。
日本ではベーコンは豚の腹部分、ばら肉(ベリー)から作られることが一般的です。
ばら肉は豚肉の脂肪が多い部位で、長期間の塩漬けや燻製(くんせい)などの加工を経て作られます。
塩漬けによって水分を抜き、燻製によって風味を加えることで、ベーコン独特の塩味とスモーキーな香りが生まれます。ベーコンはしっかりとした食感と濃い味わいがあります。
一方、生ハムは豚のももやヒレなどの部位から作られます。
生ハムは塩漬けや乾燥、熟成などの工程を経て作られることが一般的です。
ハムの製法は地域や文化によって異なりますが、一般的には塩漬けと熟成が主な工程です。
生ハムはベーコンよりも柔らかい食感を持ち、風味も異なります。
また、ハムは通常、スライスされてサンドイッチやサラダなどに使われることが多いです。
生ハムじゃないハムは燻製にしたり茹でたりする。
要約すると、ベーコンは豚の腹部分から作られ、塩漬けと燻製によって塩味とスモーキーな香りが特徴です。
一方、ハムは豚のももやヒレなどから作られ、塩漬けと熟成によって柔らかい食感と独特の風味があります。
使われるお肉
ベーコンもハムも豚肉で作るのがメジャーな作り方です。
豚肉に味付けして作るものです。
牛肉や鶏肉でも作られますが基本は豚肉
使われる部位が違う
基本的には
- ベーコンは、ばら肉
- ハムは、もも肉
元々、ハムはもも肉を差す言葉です。
ロース肉で作る、ロースハムは日本ではよく食べられるけど海外ではそこまでメジャーではない感じですね。
ベーコンにもロースベーコンやショルダーベーコンがある。
他にもイタリアベーコンと言えるパンチェッタは燻製をせずに塩漬けした豚ばら肉を乾燥・熟成したものです
ベーコンとは?
ベーコンは豚のばら肉を燻製にしたものです。
ヨーロッパで作られ続けた料理で日本でも朝食に使われたりしています。
ベーコンの語源は?
説が3つあり
ドイツ、ゲルマン人が使っていたゲルマン祖語では「Bacon」は背中を意味する言葉がベーコンの語源になったという説
古いドイツ語で豚のわき腹肉を塩漬け燻製したものをさすbahhoが古いフランス語でbaconになったという説
16世紀の政治家であり哲学者でもあり随筆家のフランシス・ベーコンが大量にベーコンを作らせたからベーコンになったという説
ベーコンの発祥国はどこですか?
ベーコンの発祥は紀元前数世紀ごろのデンマークと言われており
当時の海賊たちが豚の塩漬け肉を火で炙って保存していたのですが
ある日、湿った薪から出る煙に燻された塩漬け肉が長期保存に向いているというのが分かり
それがベーコンの原型になったと言われている。
世界的にベーコンが広まったのフランシス・ベーコンが大量に作らせたからですね
日本にベーコンが伝わったのは幕末の頃、ドイツ式のベーコンをカール・ブッチングハウス氏が製造方法を伝えました。
ベーコンの作り方
ベーコンの作り方は以下の手順で行われます。
- 豚のばら肉(腹部分)を準備します。通常は豚の脂肪が多い部位が使用されます。
- ばら肉を塩漬けにします。塩と香辛料を使ってばら肉全体に均等に塩をまぶします。塩漬けの時間はばら肉の大きさや好みによって異なりますが、通常は数日から一週間程度です。塩漬けによって水分が抜け、ベーコンの保存性が向上します。
- 塩漬けが終わったら、ばら肉を洗い流して余分な塩を取り除きます。その後、ばら肉を水でしっかりと洗い流すか、水に浸して塩抜きを行います。これにより、塩気を調節し、ベーコンの塩味を調整します。
- ばら肉を燻製にかけます。燻製にはさまざまな方法がありますが、一般的には燻製器や炭火で行われます。燻製の時間や燻製材料の種類によって、ベーコンに与えるスモーキーな風味が異なります。燻製の時間は数時間から数日にわたることもあります。
- 燻製が終わったら、ベーコンを冷やしてからスライスします。スライスの厚さは好みによって異なりますが、一般的には薄切りが一般的です。
以上が一般的なベーコンの作り方です。自宅での製造には専門の設備や知識が必要な場合があるため、安全に行うためには適切な指示や注意が必要です。
市販のベーコンも広く入手可能であり、手軽に楽しむことができます。
ハムとは
豚肉で作る加工肉でありサラダやサンドイッチに使われる。
ボンレスハムやロースハムに生ハムなどいろいろな種類がある。
ハムの原木という生ハムの塊も売られている。
ハムの語源
ハムは英語でhamと書き、「動物のもも」を意味する言葉でしたが
現在では「豚のもも肉を塩漬けにした加工食品」という意味で使われる。
人間のもも裏をハムストリングというのもこのため
ハムの発祥国はどこですか?
詳しい情報は残っていない
ハムの発祥は古代ローマ時代のフランス(当時のガリア)という説がある。
メソポタミア文明でソーセージの原型が作られていたり
古代ローマ時代には宴会でハムが使われていたなどという話もある
古代ローマ時代からハムは食べられてきたらしい。
そのためかイタリアでは生ハムなどが食べられている。
ソーセージやハムといえばドイツのイメージだが
ドイツは痩せた土地が多く家畜を育てて食べるのがもっとも効率的でした。
冬には餌がなくなり豚を育てられなくなるため、豚を潰してソーセージやハム、ベーコンなどを作っていた。
ハムの作り方
- 豚肉の選択と下ごしらえ: ボンレスハムには一般的にもも肉が使用されます。豚肉の新鮮さと品質に注意し、余分な脂肪や皮を取り除きます。また、必要に応じて肉を形成し、ムネ部分に紐を巻いて形を整えます。
- 塩漬け: 豚肉を塩で覆い、均等に塩をまぶします。塩漬けによって肉の水分が抜かれ、保存性が向上します。塩漬けの時間は肉の大きさや好みによって異なりますが、通常は数日から数週間程度です。
- ソミュール液に漬け込む: 好みに応じて、ボンレスハムに風味を与えるための香辛料やハーブを使用することがあります。代表的な香辛料にはニンニク、黒こしょう、ローズマリー、タイムなどがあります。
- 洗い流し: 塩漬けが終わったら、豚肉を十分に洗い流して塩分を取り除きます。この工程はハムの塩味を調整するために行われます。洗い流した後は、肉を水に浸して塩抜きを行うこともあります。
- 乾燥させてから燻製にする。場合によってはその後、スチームで蒸し上げたりする
- 料理または保存: 熟成が終わったら、ボンレスハムを調理して食べるか、適切な方法で保存します。ボンレスハムはスライスしてサンドイッチやオードブルに使われることが一般的です。
なお、ハムの製造は専門的な知識や設備が必要な場合があります。また、自宅で完全に製造するのは難しい場合もあります。市販のボンレスハムを購入することで手軽に楽しむことができます。
生ハムとハムの違い
生ハムは文字通り、生(なま)である事が普通のハムと違うところ
通常は燻製にしたり茹でたりするハムですが生ハムは熟成期間を長くして火を通さずに作ります。
ベーコンとハムどっちがカロリーが高い?
ハムのほうがカロリーは低い
ベーコンはバラ肉を使っているからカロリーは高くなる。
脂身たっぷりだからカロリーが高い
まとめ
ハムとベーコンの違いとは
- ベーコンはバラ肉、ハムはもも肉
- ベーコンは塩漬けしてから燻製
- ハムは生ハムとハムの二種類がある
- 生ハムは塩漬けにしてからじっくり熟成する
- ハムは塩漬けにして燻製したり茹でたりする
- ベーコンの発祥は紀元前のデンマーク
- ハムの発祥は明確な説はないが古代ローマ時代のフランスという説がある
割りと違うというか似て非なるものですね。
単純に肉の部位が違うというのもあるし、作り方も燻製がメインのベーコンに対して
ハムは長期熟成させて生で食べたり、燻製にしてから更に火を通したりする。
作り方を見るに全く違う食べ物というのが分かりますね
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ