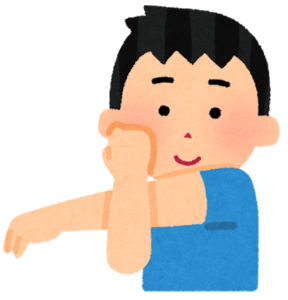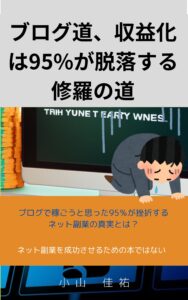スポーツや武道では脱力をしろ!と指導されますが言うのは簡単、実践するのは難しい
脱力とは如何なる状態なのか?
グニャグニャと寝転がる猫みたいな体でしょうか?
脱力とは何か?力を抜く事のメリットが分からないですよね?
まずは力みがなぜ良くないのかを解説します。
脱力と言われるけど、極めるのは難しい概念です。
矛盾せずに解釈していこうと思います。
力みはなぜ良くないのか?
力みがなぜ良くないのか?筆者は二つの理由があると思っています。
端的に言うとアクセルとブレーキを同時に使っている感じです。
関節を固定したり力を出し続けるのには良いかもしれませんが常にその状態というのはデメリットが多い
1、疲れる
これは単純に筋肉を収縮させ続けるのは難しいし疲れる。
試しに力こぶを作って1分くらい全力で力んでみてください
多分、二の腕がめちゃくちゃ疲れるはず
2、動きが悪くなる。
力みというのは体の動きが悪くなる原因にもなる。
筋肉に力を入れるという意図的に筋肉を収縮する動きはスピードが出なくなるし筋肉の連携が上手くいかなくなる。
腕を力ませると肩甲骨など体幹の力が使えない事があります。
力みが発生した時点で体幹と手足の連携は崩れてしまうようです。
3、加えられた力に対応できない
力んでいると筋肉が体を固定する事に使われてしまい加えられた力に応じる力が少なくなる。
常に一定の力を出し続ける状態では外部からの力に対して対応しづらい
四方八方から力を加えられた時に力みがあると対応できない。
剣道をやってる筆者の体験だが竹刀を強い力で握り込んでいると弾かれやすい。
弾かれるというか相手の竹刀が強い力で竹刀を打ったら耐えられない。
緩く握り竹刀が弾かれそうになった時だけ相応の力で対応する方が弾かれない。
4、力んだ後は緩むしかない
常に力が入っているわけじゃなくて
力んだ後は必ず緩む瞬間がある。
姿勢が悪くて力みがあったり自律神経の乱れであろうと必ず緩みは発生する。
それはスキになる。
脱力とは?
脱力と言われてもピンとこないかもしれません。
脱力とは筋肉の緊張がない状態を言います。
つまり、筋繊維が収縮してない状態
完全な脱力はかなり難しいと言えます。
逆に体を力ませる事は簡単で誰でも出来ます。
体の力み関して考察すると
一般的に
- 力んだ状態(肩などに力が入る)
- 脱力した状態(リラックスしている)
- 達人の脱力(正しい姿勢で無駄がない)
という感じになると考察。
脱力とは余計な力を使わない事です。
例えばドアノブを回すのに腕の筋肉を総動員させるヤツはいない
力みはエネルギーロスにつながる。
力むよりも効率よく関節が使える事の方が大事
ボールを持ったりコップに水を注いだりする時に余計な力を入れたりはしない。
つまり余計な筋収縮をしないというのが脱力
スポーツで強い力を出そうとすると力みがちです。
ですが力みを消すと自然な動きで強い力を出力できます。
スポーツで言えば野球のピッチャーが早い球を投げようとして力んでしまうとか
ボクサーがパンチの威力を出そうとして力んでしまう
これは強い力を出力しようとして余計な部分に力を入れているからです。
筋弛緩法(きんしかんほう)とは?
一般的に力んでしまう体を脱力させる方法は
- プログレッシブ・マッスル・リラクゼーション法(PMR):筋肉の収縮と緩和を交互に繰り返すことで、筋肉の緊張を解消する方法です。
- 自律神経反応療法(ANR):深い呼吸、瞑想、視覚化、想像などを使って、身体のリラックスを促す方法です。
- マッサージ療法:手や機械を使って、筋肉の緊張を和らげる方法です。
などがあります。
プログレッシブ・マッスル・リラクゼーションのやり方は
- 静かな場所でリラックスした状態になります。
- 体の部位を一つ選び、その筋肉を最大限に収縮させます。この時、数秒間収縮した状態を維持します。
- 筋肉を緩めます。この時、収縮した状態から徐々に緩めるようにします。
- 次の部位に移り、同じように収縮と緩和を繰り返します。全身の主要な筋肉群を順番に行っていくことが一般的です。
- 最後に、全身を一度リラックスさせます。
肩に力が入ってしまう状態を解決します。
この方法で力んだ状態から脱力した状態に変えていきましょう。
達人の脱力とは?
一般的に立つだけでも人間は随意筋が動いてしまいます。
というのも体にクセがついてるからです。
足、太ももなどで体が倒れないようにブレーキの役割りをしている場合もある。
そういった筋収縮をしないように立つ
骨で立つ事が大切。
筋肉は姿勢が悪いとそれを補うために使われる。
そのため、大体の人に力みがあると思われます。
赤ちゃんのように骨格で立つ事が達人の脱力です。
無駄な力が入っていないから体を動かしやすいし関節も上手に使えるようになる。
スポーツにおいて力みをとる事でパフォーマンスが向上するのは間違いない
サッカーなどで相手にぶつかったりボールを取られないように防いだりします。
そういう時に脱力が出来ていれば強い
余計なブレーキが、かからないためです。
深い脱力をするには?
脱力するためには姿勢を正す事が大事。
正しい姿勢というのは骨格で立つ事を言います。
正しい姿勢と言われてもピンとこないと思います。
放課後の教室掃除中に箒を手の平に乗せてバランスを取る遊びをした事がある人は多いと思います。
正しい姿勢とはあれを人体と地面でやる事です。
筋肉が固くならない、前腿に力が入ったら重心を移動する
ハムストリングに力が入ったら前に倒す
このように常にバランス感覚を磨いていく事が脱力の極意
そうすると体はバランスを取り始める。
筋肉が使われたら重心を移動するからです。
ただし、姿勢を整えるというが非常に難しい。
人間は10~20年と生きていると体に癖がつく
体に癖がつくというのはひどいと猫背や反り腰になってしまう。
そういった癖を無くしていかないといけない。
一般的な正しい姿勢とはこんな感じ
- 頭がまっすぐに立っていること:肩のラインと耳のラインが一致していることが理想的です。
- 肩が下がっていること:肩が前方に出ていると、首や背中の筋肉に負担がかかります。
- 腰がまっすぐに立っていること:腰が前方に出ていると、腰の筋肉や関節に負担がかかります。
- 足が肩幅程度に開いていること:足が近すぎると、膝や足首に負担がかかります。
- 膝が軽く曲がっていること:膝を伸ばしすぎると、膝の関節に負担がかかります。
- 足裏全体で立っていること:かかとやつま先に負担がかかるのを避けるためにも、足裏全体で体重を支えるようにします。
更に自分で体の位置を調整する必要があります。
体格や骨格は人それぞれ違うため他人がこれが正しいと判断するのは難しい
この状態から体と対話していき力みを取る事が大事です。
更にこの状態から腰を入れお腹を張る事で骨盤底筋群なども使える状態にしていく
背骨の関節を動かしてベストポジションを探すなどの鍛錬が必要になる。
かなり簡単そうに書いているけど、どれもこれも難しい作業だし
精密機械のようなバランスを常に取るのは長い鍛錬が必要になる。
武道では立禅などを行ったりする。
中国武術で馬歩の状態で体をゆらゆら揺らしているのは体の脱力を深めているからです。
もちろん出来る人は少ない
脱力のメリット
人間の体は練習して癖を直さないと筋肉で立ってしまう。
骨格で立つのは制御が難しいからです。
しかし、メリットは大きい
脱力する事で使える関節は増えます。
人間の体には約260個の関節があります。
普通は使えていない関節が使えるようになると
体の動きから行動を読まれない。
端から見ると棒立ちに見えても体の内側では準備が出来ている状態を作りやすい
とっさの動きが早くなる
余計な力が入らないため肩こりなどにならない。
単純に強張っている筋肉がないから体を動かしやすくなります。
柔らかくしなやかな動きができるようになります。
単純に使える関節が増えるから
筋肉の柔軟性というよりも筋肉が上手く連動して動くようになるからですね。
脱力して体がニュートラルな状態なら新しい動きも覚えやすい。
脱力によってインナーマッスルが動くようになります。
体の奥から小さいインナーマッスルがまず動いて大きなアウターマッスルが動くため
動作が小さいのに大きな力が出せたり力のロスが小さい
力みがあると外側の筋肉ばかりが動くため力のロスが大きいし
小さな動きが出来ないため無駄が多くなる。
ミニ四駆で遊んだ事がある人なら分かると思いますが
モーターについているギアは絶対に一番、小さいものが使われます
小さいギアから動かすのが一番、負荷が小さいからです。
体も同じでアウターマッスルに力が入っているというのはミニ四駆で言えば一番、大きな外側の歯車から動かすようなもので効率が悪い
体の中心、脊椎に近い筋肉から動かすのがベストと言えます。
まとめ
一般的な脱力方法としてはプログレッシブ・マッスル・リラクゼーションやストレッチなどが有効ですが
深い脱力になると姿勢を整えたりする事が大事になる。
姿勢を整えると言っても他人が見て判断できるレベルではなく微調整をしつつ体をほぐしていく方法になります。
脱力すると骨で立つ感覚が得られ重力を感じるようになるし、重さを使えるようになります。
筋肉を連動させた動きが出来るようになったり新しい動き覚えやすくなります。
かなり難しいですが練習として取り入れるのはおすすめ
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
体幹の使い方とは?体幹をまとめる?頭蓋骨から尾てい骨までをどう使う?【考察編】