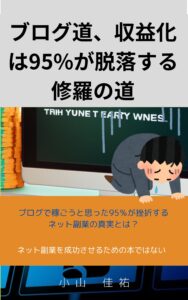日本では玄関で靴を脱いで家に入ります。
欧米では土足で家の中に入る国がほとんどといえます。
なぜ日本では家の中で素足、家の外で靴を履くのか?
それは日本の気候や神道の考えなども影響している。
歴史的にも玄関で靴(履き物)を脱ぐというのは弥生時代から行われていたと言われています。
玄関で靴を脱ぐ理由?
いろいろ考える事ができますが
- 現実的な問題
- 宗教的な視点
この二つから靴を脱いでいた。
日本は昔から高温多湿で靴をずっと履いていたら蒸れる。
雨も多いし湿気もすごい、四六時中ずっと靴を履いていたら水虫になってしまうし何より不快感がある。
水虫を防ぐためにも家では靴を脱いでいた。
更に高温多湿という事は草鞋やゲタなどの履き物であっても土で汚れる。
日本は畳で寝たり、床に直接、布団を敷いて寝るため床は清潔にしないといけなかった。
更に言えば土のついた床を放置していれば腐ってしまうしカビも生えてしまう。
そのため靴を脱ぐのが合理的。
また、神道にはウチとソトを分けるという考え方があり
家のウチに穢れを入れない
家の中というのは安全な場所であるからそういう物を入れないために履き物を脱いでいた。
家の中というのは神聖な場所であり裸足で過ごしても良いという考えがあったようです。
平安時代の貴族も戦国時代の武将も家の中では裸足であったというわけです。
土足文化になったのは何故?
革靴の起源はゲルマン民族が寒さや砂ぼこりから足を守るために作られたそうです。
靴と言うのは防寒具であり足を守る存在。
日本人の感覚からすると土足で家に入るなんて汚いと思ってしまいますね。
土足文化の国と日本の違いはそれは安息の場所が違うからです。
日本では昔から畳の上で寝ていました。
今でこそベッドが普及していたりしますが昔はベッドです。
昔の感覚で言えば畳=ベッドと言ってもいい
土足文化と言ってもベッドの上では靴を脱ぎます。
つまり、ベッドこそ安息の場所と考えていたというわけです。
日本の場合は家の中が神聖な安息の場所であるという考えのため靴を家に入る前に脱ぐ
土足文化の国ではベッドこそが安息の場所であるためベッドに入る前に靴を脱ぐというわけです。
海外でも玄関で靴を脱ぐ文化はある
実はアジア圏の国では靴を脱ぐ習慣がある国は多い。
特に東南アジアは昔から靴を脱ぐ文化があるようです。
調べると高温多湿な地域では靴を脱ぐ習慣が根付いている。
タイでは外で靴を脱いで家に入る。
昔のタイは素足で活動して家に入る前、水で足を洗ってから家に入っていました。
この習慣が変化して家の外で靴を脱ぐようになったと言われています。
お隣の韓国は似た文化だからかもしくは併合された時に導入されたのか靴を脱ぐ習慣があります。
台湾も靴を脱いで家に入るそうです。
中国では靴を脱ぐ文化と靴を履いたままの文化があり地域によって違うなんてこともあるそうです。
寒い地域では靴という防寒具を脱がない、家に玄関もなくふかふかのマットに座る時やベッドで寝る時に靴を脱ぐ
中国南部では靴を脱いで家に入るそうです。
さすが多民族国家
トルコでは穢れ(けがれ)を家に持ち込まないために靴を脱ぐそうです。
アラスカ、カナダ、ノルウェーやスウェーデンなどは靴を脱がないとストーブの暖かさを感じられなかったりフカフカのラグを汚さないために靴を脱ぐそうです。
現代では土足文化のある国でも家の中では靴を脱ぐ、もしくはスリッパを履くという文化が浸透しつつあるそうです。
外履きを脱いで上履きに履き替える国
北ヨーロッパやオーストリアではブーツなどの屋外作業用の靴では家に入らない
上履きに履き替える
パーティーなどでもタキシードなどと一緒で靴もフォーマルなものと考えられているため
上履きを別に持ってきて履き替えるという文化がある。
まとめ
日本人が玄関で靴を脱ぐのは神道の考え
ウチとソトという考えがあり神聖な場所である家の中にソトの穢れを入れないために靴を脱ぐ
玄関から家に入る事を
玄関に上がる
なんて表現される、高温多湿なため段差があるから家に上がるや玄関に上がるという言葉が使われている。
また日本では床に座りお膳でご飯を食べていたから土足で家に入るなんてのは考えられないです。
日本以外でも高温多湿な地域、東南アジアでは靴を脱ぐ習慣があるそうです。
中国は縦にも横にも広いから土足文化と靴を脱ぐ文化が混在しているそうです。
現代では靴を脱ぐ習慣が広まりつつあるみたいですね。
ではでは(^ω^)ノシ
この記事もおすすめ
日本のおやつはいつから? 歴史は意外と浅い?3時のおやつが広まったのはいつ?